相続の手続を行う際、被相続人の財産をどのように分けるかを決める前提として、まず「誰が相続人であるか」を正確に確定させる必要があります。これは一見すると簡単な作業に思われがちですが、実際には複雑な調査を要する場合も多く、特に法定相続人の人数が多かったり、家族関係が複雑だったりする場合には、その調査に想像以上の時間と労力がかかります。
たとえば、生前にほとんど連絡を取っていなかった親族がいたり、被相続人に過去の婚姻歴や認知した子がいる可能性があるといったケースでは、戸籍をたどること自体が非常に煩雑になります。また、相続人となるべき人物が転居を繰り返していたり、連絡先が不明で所在不明となっているような場合には、法的な調査に加えて実地的な手法も必要となることがあります。
こうした状況においては、法律に基づいた文書取得や行政手続に精通した「行政書士」と、現地での調査や聞き込みを得意とする「探偵」の双方の専門知識と技能を組み合わせることで、より正確かつ効率的に相続人の確定や所在の把握を進めることが可能になります。
本記事では、行政書士と探偵、それぞれの立場から「相続人を探す方法」について詳しく解説していきます。相続手続に必要な戸籍調査の基本から、実際にどのように行方不明者を見つけるのかまで、実務の現場で役立つ知識を幅広く紹介します。相続手続の第一歩として重要なこのステップを、確実に進めるための参考にしていただければ幸いです。
相続人を探す方法は?行政書士にできること

行政書士は、本人からの委任や職務上請求制度を通じた戸籍の調査により、法的に相続人を特定することが可能です。
相続手続を進めるうえで、誰が相続人であるのかを明らかにすることは最初にして最大の課題といえます。
行政手続に精通した専門家である行政書士は、戸籍の取得にとどまらず、記録内容の分析や家族関係の整理まで対応できるため、相続人の調査において非常に心強い存在となります。
以下では、戸籍の種類、調査の難しさ、そして取得に関する実務的な制限について詳しく見ていきます。
戸籍の調査
戸籍の種類
戸籍制度は、日本の家族関係を記録するための制度として古くから運用されてきました。相続手続において活用される主な戸籍には、現在戸籍、除籍謄本、改製原戸籍の三種類があります。
現在戸籍は、現時点でその戸籍に記載されている人々、すなわち生存している者の情報が記録された戸籍です。現在の家族構成や続柄、転籍や婚姻といった最新の身分関係が確認できます。
除籍謄本は、かつてその戸籍に記載されていた全ての人物が転籍や死亡、婚姻などによって除かれ、現在は誰も在籍していない状態の戸籍を意味します。かつての家族構成や婚姻・離婚歴、死亡日などが記載されており、被相続人の過去の状況を知るために重要な役割を果たします。
改製原戸籍は、法改正により戸籍の様式が変更された際に、それまで使われていた旧形式の戸籍として作成されたものです。この戸籍には、旧字体で記載された情報や、現行戸籍には記録されていない過去の身分関係が含まれており、相続人の特定には欠かせない資料となります。
相続手続では、これら三種の戸籍を相互に突き合わせながら、被相続人の出生から死亡に至るまでの全戸籍を取得し、誰が相続人に該当するかを法的に確定していく必要があります。
戸籍の調査の難しさ
戸籍の調査は、表面的には単なる書類の収集に見えるかもしれませんが、実際には専門的な知識と根気を要する作業です。被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得するには、まず現在戸籍を取り寄せ、そこから一つ前の戸籍へとさかのぼり、順を追って過去の戸籍をすべて確認していく必要があります。
しかし、実際の戸籍調査は一筋縄ではいきません。被相続人が複数回の転籍をしていた場合、その都度本籍地が変わっている可能性があるため、調査対象となる自治体も複数に及びます。それぞれの自治体に対して個別に請求を行い、時には過去の転籍先を役所に電話で問い合わせる必要も出てきます。
また、古い戸籍には旧字体が使用されていたりすることもあります。加えて、兄弟姉妹の存在、養子縁組、認知された子、婚姻歴など、見落とされがちな情報も相続人の範囲に大きく関わってきます。これらを見落とすと、相続人の漏れという深刻な事態につながりかねません。戸籍の調査を正確に行うには、家族関係の法的理解に加え、読み解き能力や資料分析の経験も必要です。
戸籍は誰でも取得できる?
戸籍は、国民のプライバシーや個人情報を含む重要な公文書であるため、自由に取得できるものではありません。原則として、その戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫といった直系卑属にあたる者が取得の対象とされています。
それ以外の第三者が戸籍を取得する場合には、正当な理由が求められます。たとえば、遺産相続手続において相続人を確定するために、被相続人の戸籍を取得する必要があるような場合がこれに該当します。ただし、正当な理由があるだけでは足りず、それを裏付ける書類、具体的には委任状や依頼文書、相続関係を証明する資料などを添付する必要があります。
実務上、自治体によって運用の厳格さに違いがある点も注意が必要です。ある市区町村では比較的スムーズに取得できた戸籍が、別の自治体では再提出や追加説明を求められることもあります。このような場合に、行政書士が関与していれば、請求理由の書き方や必要書類の整備を適切に行えるため、請求が却下されるリスクを大幅に減らすことができます。
また、行政書士には戸籍を職務上の目的で取得できる「職務上請求制度」が認められており、一般の方が行う戸籍請求とは手続も立場も異なります。この点については次項で詳しく解説します。
【関連記事】
戸籍調査で行方不明者を探す!専門家が教える方法
行政書士による職務上請求
職務上請求とは
行政書士には、委任を受けた正当な案件について、戸籍謄本や住民票、除票といった各種公的資料を取得するための特別な手続が認められています。これが「職務上請求制度」と呼ばれるものです。この制度は、行政書士法に基づく業務遂行の一環として運用されており、依頼人の権利義務に関わる調査や手続を適法かつ迅速に行うために重要な役割を果たしています。
行政書士は、一般の方と異なり、本人確認書類や委任状をその都度添付することなく、職務上請求書と呼ばれる専用の用紙を用いて請求を行うことができます。この請求書は行政書士の氏名や登録番号、事務所所在地などが記載された書類であり、提出先である役所もこれを受け付けることで、迅速な発行を行える仕組みとなっています。
ただし、職務上請求が認められるのはあくまで「行政書士としての職務」に基づく場合に限られており、無関係な第三者の情報を不正に取得するような目的での使用は厳に禁じられています。
職務上請求のメリット
職務上請求制度の最大の利点は、時間的・手続的な負担を大きく軽減できる点にあります。たとえば、被相続人の出生から死亡に至るまでの一連の戸籍を請求する場合、通常の請求であればそれぞれの自治体に個別に委任状や相続関係を証する戸籍を添付し、理由を詳細に説明した文書を用意しなければなりません。
一方、行政書士が職務上請求を用いる場合には、そうした煩雑な添付書類を省略でき、請求書一通で複数の戸籍を一括して請求することが可能です。さらに、相続関係の案件では、転籍や婚姻、離婚などによって本籍地が複数にわたるケースも珍しくありません。全国の自治体に散らばった戸籍を短期間で集めるには、職務上請求の活用が不可欠となるのが現実です。
行政書士が介在することにより、書類の不備や返戻のリスクを最小限に抑えつつ、必要な情報を的確に集めることができます。依頼人にとっても、手続の透明性が高まり、調査の進行が明確になるという大きなメリットがあります。
探偵は職務上請求できない
職務上請求制度は、行政書士や弁護士、司法書士など、法令に基づいて特別な業務を行うことが認められている資格者に限って付与されている権限です。探偵やその他の無資格者は、この制度を利用して戸籍や住民票を取得することはできません。
担当係とのやり取り
戸籍を郵送で請求する場合
戸籍の請求は、役所の窓口で直接行うだけでなく、郵送によっても手続を進めることが可能です。特に遠方に本籍地がある場合や、多数の自治体にまたがって請求を行う場合には、郵送による請求が現実的な方法となります。
しかしながら、郵送での戸籍請求には特有の注意点があります。提出された請求書の記載内容や添付書類に不備や疑問点がある場合、自治体の担当係から請求者に対して電話で確認が入ることがあります。この確認の電話では、請求理由や請求対象者との関係性について詳細な説明を求められることがあり、十分な知識がないままに対応すると、誤解を招いたり、場合によっては返戻処理されてしまう可能性もあります。
行政書士であれば、こうしたやり取りにも的確に対応できます。あらかじめ請求目的と関係性の説明を整理しておくことで、職員の質問にも的確に答えることができ、電話対応を通じてスムーズな発行につながります。また、郵送請求時の添付資料の整備や、役所ごとの様式や運用の違いにも精通しており、必要に応じて補足説明文を添付するなど、柔軟な対応が可能です。
【関連記事】
お父さんを探す方法|探偵行政書士が教える再会への道
母親と再会したい方必見!母親の探し方徹底ガイド
相続人を探す方法は?探偵業者として

相続人の調査において、書類上の記録だけでは所在や現況を把握しきれない場合があります。たとえば、住民票が長らく異動されておらず、記載された住所に実際は誰も住んでいないようなケースや、意図的に連絡を絶って所在を隠している相続人がいるといった状況が典型です。
そうした場合、戸籍や住民票といった公的記録に基づく調査だけでは限界があり、実際の動きや現場の状況を確認できる探偵業者の力が求められる場面が出てきます。
探偵業者は、現地調査や聞き込みといったフィールドワークに特化した専門家です。書面には現れない情報や、関係者の動き、近隣の生活環境を丁寧に追跡し、実在する相続人の「現在地」や「日常的な所在状況」を確認することができます。こうした探偵業者の調査は、行政書士が行う戸籍調査と異なる性質を持ち、双方の役割がうまく補完し合う形で機能することになります。
戸籍の調査はできる?
相続人を探すには、まず戸籍をたどることが基本となりますが、探偵業者がこの戸籍の取得を行うことは原則として認められていません。探偵業に従事する者が戸籍を役所に請求する行為は、法的に制限されているのが現状です。
これは、行政書士法の規定によるもので、同法第1条の2において「官公署に提出する書類」や「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」を業として作成することが行政書士の業務であると定義されています。そして、第19条では、行政書士でない者がこれらの業務を反復継続的に報酬を得て行うことを明確に禁止しています。
戸籍謄本の取得手続は、まさに市区町村という官公署に対して行う行政手続であり、その過程では請求理由の記載や本人確認の根拠書類の提出が求められます。これを業務として行うには、法的な根拠が必要であり、行政書士や弁護士などの有資格者でなければ行えません。
したがって、探偵業者が依頼を受けて戸籍を取得することは、たとえ委任状があったとしても違法行為とされるおそれがあります。さらに、その行為が継続的に行われていた場合には、行政書士法並びにその他法令違反として刑事罰の対象にもなり得ます。
探偵業者が相続人の調査に関わる場合には、あくまで実地調査を中心とした範囲に留め、公的文書の取得については行政書士や弁護士など、正規の資格を持つ専門職と連携する必要があります。
| 行政書士法第19条(業務の制限) 1 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。 |
実地調査・聞き込み
探偵業者の最大の強みは、現地での動きに即した調査力にあります。相続人の居所が不明である場合、あるいは戸籍や住民票上の住所にその人物が実際には住んでいないと推測される場合、現場に赴いての確認作業が必要不可欠です。
探偵業者は、依頼に基づいて現地周辺の聞き込みを行い、近隣住民や管理人などからその人物に関する情報を得ることができます。たとえば、過去に住んでいたがすでに転居したことが確認されたり、特定の曜日や時間帯に姿を見かけるといった証言が得られれば、所在確認の大きな手がかりになります。
また、探偵業者は必要に応じて張り込みや尾行といった手段も講じます。もちろん、これらの行為は探偵業法に則って適正に行われる必要があり、違法な手段は厳しく禁じられていますが、合法的な範囲内での行動によって、現在の生活状況や行動パターンを把握することが可能です。
相続人を探す方法/結局どっちがいい?

相続人の調査においては、すべてを一つの手法だけで完結させることができるとは限りません。
行政書士と探偵、それぞれに得意とする領域があり、事案の内容に応じて適切な手段を選択することが重要です。
法律に基づいて正確に戸籍を収集し、法定相続人を確定するためには行政書士の知識と権限が不可欠です。一方で、実際にその相続人がどこに住んでいるのか、あるいは連絡が取れる状態なのかといった実態把握の面では、探偵業者の機動力が非常に有効となる場面があります。
どちらか一方だけでは補いきれないケースも少なくないため、調査の目的と現状を明確にしたうえで、行政書士と探偵を適切に使い分ける、あるいは連携させることが、円滑な相続手続の第一歩となります。
第一に行政書士
相続人の調査において最も基礎となるのは、戸籍謄本や住民票などの公的記録に基づいて、誰が法定相続人であるのかを正確に確認する作業です。これは単なる名簿作成のように見えるかもしれませんが、法的な知識と正確な書類の読み取り能力が求められる、非常に繊細な作業です。
行政書士であれば、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍を体系的に収集し、転籍や婚姻、養子縁組といった事実を一つひとつ確認しながら、血縁関係や婚姻関係に基づく相続人の範囲を明確にすることができます。
単に戸籍を取り寄せるだけでなく、そこに記載された情報を読み解き、正確な相続関係図を作成することができるという点で、一般の方が行う調査とは一線を画します。また、行政書士には職務上請求制度という強力な手段が認められており、依頼者のために戸籍や住民票の請求を迅速かつ的確に行うことができます。
全国の自治体をまたいで複数の戸籍を収集する必要がある場合でも、行政書士であれば無理なく対応できる体制が整っています。さらに、遺産分割協議書の作成や相続関係説明図の整備など、調査後の法的書面作成についても行政書士が一貫して対応可能です。そのため、相続人調査だけでなく、実際の手続きにスムーズにつなげられるという点においても、非常に大きなメリットがあります。
第二に探偵業者
一方で、法的に正しい相続人が戸籍上で判明したとしても、その人物が実際にどこに住んでいるのかが不明であるというケースも少なくありません。たとえば、住民票が古いままで更新されておらず、すでにその住所に住んでいない可能性がある場合や、意図的に住所変更を怠っている場合などが該当します。
こうした場合においては、行政書士が収集した文書情報だけでは限界があり、現地での確認や周辺への聞き込みなど、実動による調査が必要となります。ここで力を発揮するのが探偵業者です。
探偵は、対象者の過去の居住歴や現在の所在について、地域住民への聞き込みや張り込みを通じて情報を集めます。どのような場所で生活しているのか、連絡を取るための手がかりがあるのかといった、書類では得られない実情を把握するうえで、探偵の役割は非常に重要です。
また、相続人が意図的に連絡を絶っている場合、行政書士が行う文書送付などの方法では進展が得られないこともあります。そうした状況下で、探偵が調査を行い所在や生活の実態を明らかにすることによって、次の手続へと進める道が開かれるのです。
なお、どうしても相続人の所在が判明しない場合には、最終手段として家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任申立て」を行うという法的対応が用意されています。これは、相続手続を進めるためにどうしても相続人全員の参加が必要であるが、そのうち一人の所在が不明であるという場合に、裁判所が代理人を選任して手続きを進行させる制度です。
この制度を活用するにも、調査を尽くしたことの証拠や経緯を明示する必要があるため、探偵による調査報告が補足資料として有効に機能することもあります。
行政書士と探偵、それぞれの調査は対立するものではなく、むしろ補完関係にあります。行政書士が戸籍から法的な相続人を確定し、そのうち連絡の取れない人物を探偵が見つけ出すという流れが、最も現実的で有効な対応となることが多いといえます。相続人の調査に不安を抱えている方は、どちらか一方に絞るのではなく、状況に応じて両者を組み合わせていくという柔軟な発想が求められます。
相続人を探す方法/まとめ

相続手続において、誰が相続人であるのかを正確に把握することは、すべての出発点となります。遺産分割協議や相続登記、預貯金の解約など、あらゆる手続が相続人全員の同意を前提としている以上、この調査を誤ったり怠ったりすれば、その後の手続が無効となるおそれすらあります。
相続人を調べるためには、まず戸籍を正確に収集し、家族関係を明らかにすることが必要です。この法的作業を担うのが行政書士であり、専門的な知識と法的権限に基づいて、出生から死亡までの一貫した戸籍を取得し、法定相続人を特定することができます。行政書士の職務上請求制度を活用すれば、全国の自治体にわたる広範な調査も、無理なく短期間で進めることができます。
一方で、戸籍上では確認できても、実際の所在が不明な相続人がいるという現実も少なくありません。そのようなケースでは、行政書士による文書調査だけでは限界があり、探偵による実地調査が必要となる場面があります。現地での聞き込みや張り込みを通じて、実際の生活状況や行動パターンを把握する調査力は、書類では把握しきれない「今」を追うために欠かせない要素です。
このように、相続人調査は一つの視点や手段だけで完結するものではありません。戸籍という法的根拠に基づく確認と、現地調査という実務的・現実的な確認をうまく組み合わせることで、より確実で円滑な調査が可能となります。
また、調査を尽くしても所在が分からない相続人がいる場合には、家庭裁判所の制度を利用して不在者財産管理人を選任することもできます。そのためにも、これまで行った調査の経緯をきちんと記録し、法的に説明可能な形で残しておくことが求められます。
相続人の調査には時間と労力がかかるものですが、正確かつ適法に手続を進めることで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。相続に関する調査に不安がある場合や、どこから手を付ければ良いか分からないという方は、まずは行政書士に相談してみるのが良いでしょう。必要に応じて探偵と連携する体制も整えながら、専門家の力を借りて、納得のいく相続を目指していただければと思います。
相続人調査は当事務所にお任せください

相続人の調査は、法的知識と実務経験、さらには綿密な資料収集と的確な判断力を要する繊細な作業です。当事務所では、行政書士としての専門性に加え、探偵業との連携体制を活かし、法的根拠に基づいた戸籍調査と実地的な所在確認の両面からサポートを行っております。
特に次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得したいが、転籍が多く手続が煩雑で困っている
- 相続人が誰なのか分からないため、遺産分割協議を始められない
- 戸籍上は確認できても、相続人と連絡が取れず、遺産分割が進まない
- 自分で役所に戸籍請求をしてみたが、理由の説明ができずに返戻された
- 相続放棄を検討しているが、他の相続人がどこにいるのか分からない
当事務所では、こうした複雑な相続人調査に対応するため、戸籍の取得から関係図の作成、必要に応じた探偵調査まで一括してご案内が可能です。書類作成だけでなく、各種相続手続のご相談にも幅広く対応しており、お一人おひとりの状況に応じて最適な進め方をご提案いたします。
相続人が見つからないことで手続が止まっている場合や、自分だけでは対応が難しいと感じた際には、無理に一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。初回のご相談では、今の状況やお悩みを丁寧にヒアリングさせていただき、今後の進め方をご説明させていただきます。
サービスの特徴
きめ細やかな対応
当事務所では、単なる「人探し」にとどまらず、その先にある目的達成までを視野に入れた支援を行っております。「相手は見つかったが、通知や請求をどう進めればよいのか分からない」「法的に有効な書類をどう作ればいいのか不安」といったお悩みに対し、調査と書類作成の両方を一貫して対応できることが最大の特長です。
行政書士としての法的知識と、探偵業としての実務経験を融合させることで、一般的なテンプレートや雛形では対応できない複雑な案件にも柔軟に対応してきた実績があります。個別の事情や背景をしっかりと把握した上で、依頼者様一人ひとりに最適な方針をご提案いたします。
柔軟な相談・業務対応
ご相談は、電話・メールなど、依頼者様のご都合に合わせて柔軟に対応しております。遠方の方、対面が難しい方、プライバシーに配慮したい方も、安心してご相談いただけます。
「まずは人を探したい」「発見後に書類を送りたいが内容に不安がある」こうした初期段階からでもご相談可能であり、状況に応じて通知書の作成・契約書の取り交わし支援・告訴状の作成・他士業との連携支援まで、段階的な対応をご用意しています。
明確な料金体系
ご相談内容を丁寧にヒアリングした上で、調査と書類作成の内容を明確に切り分け、必要な範囲だけに費用がかかるよう設計しております。無駄なオプションや不要な追加費用が発生しないように、事前にお見積書を提示し、明朗な料金体系をご案内いたします。
料金は、「基本料金(調査・書類作成)」+「実費(交通費・郵送費・証明書取得費等)」で構成されており、見積もりにご納得いただいてからのご契約となるため、安心してご依頼いただけます。
「費用がどの程度になるか心配」「初めてなので相場感が分からない」という方も、まずは無料相談をご活用ください。調査の目的やご予算に応じて、現実的なプランをご提案いたします。
全国対応
当事務所の調査・書類作成対応は、基本的に全国対応が可能です。調査対象者の所在がどの地域にあっても対応しており、これまでにも北海道から沖縄まで、都市部はもちろん、地方の難易度の高い案件にも数多く対応してまいりました。
また、書類のやり取りはPDF等のデータ送信、郵送、オンライン面談等で対応可能なため、ご来所いただく必要はありません。遠方にお住まいの方や、忙しくて時間がとれない方にも、スムーズにご利用いただける体制を整えております。
ご依頼の流れ
- 初回相談(無料)
まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。「誰を探したいのか」「調査の目的は何か」など、現時点でお分かりになる範囲でかまいません。ご相談内容を丁寧にヒアリングした上で、調査の可否や進め方、必要となる法的手続きについての概要をご説明いたします。 - お見積りとご契約
初回相談の内容を踏まえ、具体的な調査手法・範囲・期間、そしてその後に必要となる書類作成の有無などを明確にした上で、正式なお見積りを提示いたします。ご提示する料金には、基本料金および必要と想定される実費(証明書の取得費、郵送費等)を含み、不透明な費用は一切ございません。内容にご納得いただいた上で、正式にご契約手続きを進めてまいります。契約後もご不明点があれば随時ご説明いたしますので、ご安心ください。 - 調査開始・進捗報告
ご契約後、速やかに調査を開始いたします。調査の内容は目的に応じて異なりますが、戸籍・住民票・登記簿・SNS・電話番号情報などを適法に活用した書面調査を中心に行い、必要に応じて実地調査も組み合わせます。調査期間中は、必要に応じて途中経過をご報告いたします。ご希望があれば、調査の進捗に関するご連絡方法(メール・電話など)も柔軟に対応いたします。 - 調査結果のご報告と、次のステップのご提案
調査が完了しましたら、調査報告書をお渡しするとともに、分かりやすく結果をご説明いたします。調査によって得られた情報をもとに、本来の目的に沿った次の行動にスムーズに移行できるよう、当事務所からご提案を行います。たとえば、以下のような対応が可能です。
・内容証明郵便による通知書の作成(貸金返還請求、扶養費請求など)
・合意書、契約書の起案および文案調整(債権回収、養育費合意など)
・相続人に対する遺産分割協議書の作成と通知支援
・告訴状の起案、添付資料の整備(結婚詐欺、ストーカー、DVなど)
当事務所では、“調査して終わり”ではなく、解決までを見据えた総合対応を行っております。依頼者様が安心して次のステップへ進めるよう、全力でサポートいたします。
基本料金
当事務所では、ご依頼内容に応じて明確な料金設定を行っております。調査のみで終わらず、その後の通知書作成や契約書作成なども一貫して対応可能です。
ご相談内容に応じて個別見積りも承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
| サポート内容 | 費用 | 概要 |
| 書面による人探しサポート | 55,000円 (税込)〜 | 公的書類(戸籍・住民票・登記簿など)およびデータ調査を中心に、対象者の所在を特定します。SNSや過去の居住情報等も含めた“紙とデータ”による効率的な所在調査を行います。 |
| 通知書・契約書・合意書等の作成 | 33,000円 (税込)〜 | 所在判明後に必要となる通知書・内容証明・契約書・告訴状などを行政書士が法的根拠に基づき作成いたします。書類単体のご依頼も可能ですが、調査とのセットでご依頼いただくことでスムーズな対応が可能です。 |
| 実地調査(近畿圏限定) | 55,000円 (税込)〜 | 必要に応じて、現地訪問による実地調査・聞き込み等も対応可能です。基本的には大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山の近畿圏内を対象としており、それ以外の地域についてはご相談ください。 |
料金の詳細はこちら
お問い合わせ
下記「*」は必須回答でございます。
対応地域について
当事務所では、業務の性質や調査方法に応じて、対応地域を「メイン対応地域」と「全国対応地域」に区分してご案内しております。いずれの地域からもご依頼は可能ですが、対応のスピードや実地調査の可否に多少の違いがございます。以下をご参照ください。
メイン対応地域(迅速対応・現地対応可)
【大阪府・奈良県を中心とする近畿地方全域】
当事務所の所在地である大阪市を拠点に、大阪府・奈良県・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県など近畿圏を中心に対応しております。この地域においては、調査の着手が特に迅速であるほか、実地での張り込み・現地訪問調査・対面相談などにも柔軟に対応が可能です。
- 所在特定や行動確認のための現地調査
- 直接訪問による書類回収・通知対応
- お急ぎ案件への即日対応など
実地を伴う調査や、迅速な対応をご希望の方には、特に適したエリアです。
全国対応地域(書面・データを活用した調査中心)
【東京・神奈川・千葉をはじめ、全国各地】
当事務所では、関東圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)を含む全国の地域からのご依頼にも対応しております。このような地域では、主に戸籍・住民票・登記情報・SNSなどの書面・データ調査を中心としたサービスを提供しております。
- 書類作成(通知書・契約書・合意書・告訴状など)全国対応
- ご相談は電話・メールにて柔軟に対応
- 書類は郵送またはPDF形式での納品により全国対応可能
実地調査をご希望の場合も、地域に応じた方法をご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
これまでの対応実績(近畿全国例)
- 近畿圏(大阪市、奈良市、橿原市、生駒市、神戸市、伊丹市、西宮市など)
- 東京都(新宿区・世田谷区・足立区)
- 神奈川県(横浜市・相模原市)
- 千葉県(千葉市・船橋市・市川市)
- 愛知県・広島県・福岡県・北海道・沖縄県など
対応地域に関する補足
一部の離島や調査困難地域においては、実地対応に制限がある場合がございますが、書面調査を活用した代替手段をご提案いたします。
【関連法令】
行政書士法
探偵業の業務の適正化に関する法律

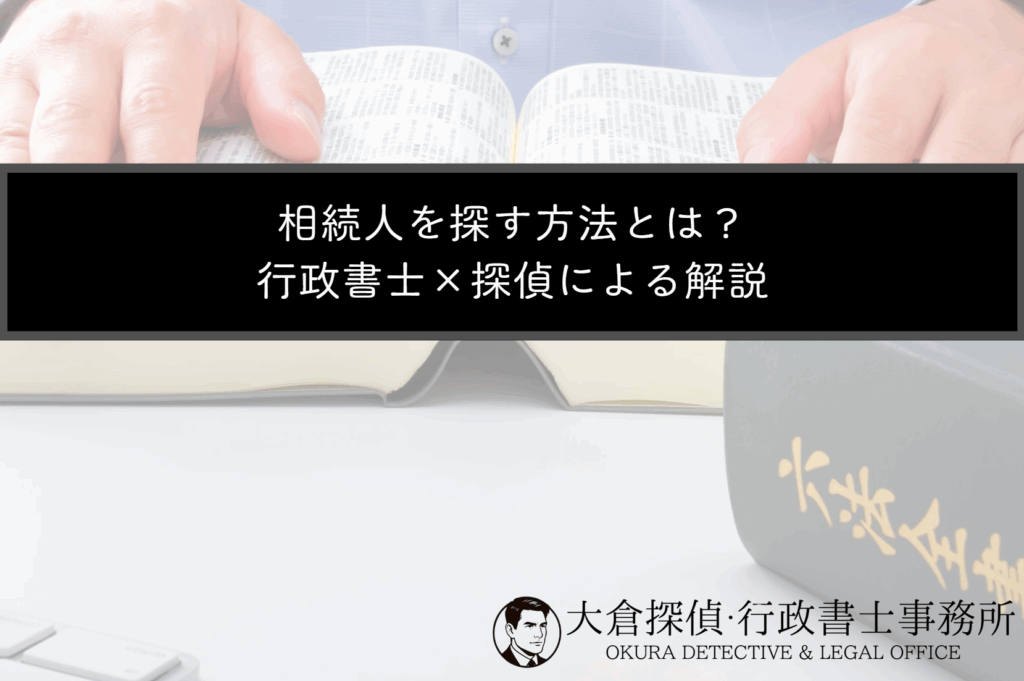
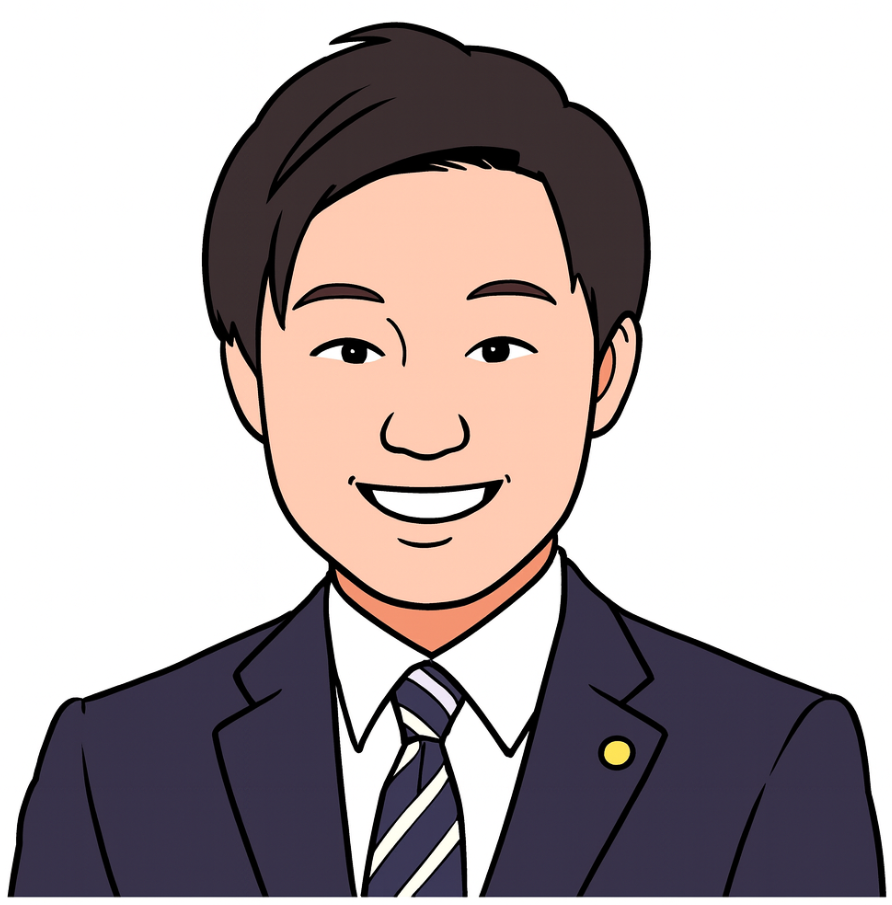
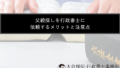

コメント